.jpg)
『万葉集』妹山、背山を詠んだ歌を集めてみました。
1-36
・此也是能 倭尓四手者 我戀流 木路尓有云 名二負勢能山
これやこの 大和にしては 我が恋ふる 紀路にありといふ 名に負ふ背の山
この山が大和にいて見たいと恋い焦がれていた背の山なのね、紀伊にあって名に負っているこの山が。
3-285
丹比真人笠麻呂徃紀伊國超勢能山時作歌一首
・栲領巾乃 懸巻欲寸 妹名乎 此勢能山尓 懸者奈何将有
[一云 可倍波伊香尓安良牟]
栲領巾の懸けまく欲しき妹が名をこの背の山に懸けばいかにあらむ
栲領(たくひれ)を肩にかけるではないが、彼女の名を口に出したいものだ。
いっそ、この背の山を妹の山と呼んでみたらどうだろう。
(一に云う。(背と妹を)取り替えてみたどうだろう)。
.jpg)
3-286
春日蔵首老即和歌一首
・宜奈倍 吾背乃君之 負来尓之 此勢能山乎 妹者不喚
よろしなへ 我が背の君が 負ひ来にし この背の山を 妹とは呼ばじ
よろしいじゃありませんか。人々が「我が背の君」と親しんで呼んできた「背の山」を
いまさら「妹の山」とは呼べませんよ。
9-1676
大寳元年辛丑冬十月太上天皇大行天皇幸紀伊國時歌十三首
| ・勢能山尓 黄葉常敷 神岳之 山黄葉者 今日散濫 |
| 背の山に 黄葉常敷く 神岳の 山の黄葉は 今日か散るらむ |
背の山はいつも美しい黄葉が散り敷いている。あの神岳の黄葉もきょうあたり散っているだろうか。
奈良の神丘の紅葉を思った歌。作者未詳
3-291
小田事勢能山歌一首
・真木葉乃 之奈布勢能山 之<努>波受而
吾超去者 木葉知家武
真木の葉の しなふ背の山 偲はずて 我が越え行けば 木の葉知りけむ
| 豊かな美しい木々が生い茂る有名な背の山、それを愛でずに行けば、木々の葉もその無骨さを知るだろうに。 |
背山 和歌山県伊都郡かつらぎ町にある山。
.jpg) 飛び越え石
飛び越え石
和歌山と奈良の県境を流れる落合川の両岸からせりだす2つの大きな岩石。間を小川が流れ、そこを渡ればもう奈良県。万葉の旅人は国境越えを目前にし、故郷に残してきた恋人や家族を想いこの石を越えたといいます。
4-543
神龜元年甲子冬十月幸紀伊國之時為贈従駕人所誂娘子<作歌>一首[并短歌]
笠朝臣金村
・天皇之 行幸乃随意 物部乃 八十伴雄与
出去之 愛夫者 天翔哉 軽路従 玉田次
畝火乎見管 麻裳吉 木道尓入立 真土山 越良武公者 黄葉乃 散飛見乍 親 吾者不念 草枕
客乎便宜常 思乍 公将有跡 安蘇々二破
且者雖知 之加須我仁 黙然得不在者 吾背子之
徃乃萬々 将追跡者 千遍雖念 手<弱>女
吾身之有者 道守之 将問答乎 言将遣
為便乎不知跡 立而爪衝
大君の 行幸のまにま もののふの 八十伴の緒と
出で行きし 愛し夫は 天飛ぶや 軽の路より
玉たすき 畝傍を見つつ あさもよし 紀路に入り立ち 真土山 越ゆらむ君は 黄葉の 散り飛ぶ見つつ にきびにし
我れは思はず 草枕 旅をよろしと 思ひつつ
君はあらむと あそそには かつは知れども
しかすがに 黙もえあらねば 我が背子が
行きのまにまに 追はむとは 千たび思へど
手弱女の 我が身にしあれば 道守の 問はむ答へを
言ひやらむ すべを知らにと 立ちてつまづく
おほきみの みゆきのまにま もののふの やそとものをと
いでゆきし うるはしづまは あまとぶや かるのみちより
たまたすき うねびをみつつ あさもよし きぢにいりたち
まつちやま こゆらむきみは もみちばの ちりとぶみつつ
にきびにし われはおもはず くさまくら たびをよろしと
おもひつつ きみはあらむと あそそには かつはしれども
しかすがに もだもえあらねば わがせこが ゆきのまにまに
おはむとは ちたびおもへど たわやめの わがみにしあれば
みちもりの とはむこたへを いひやらむ すべをしらにと
たちてつまづく
天皇の行幸につき従って、多くの付き人と出て行った我が夫。軽の路から畝傍山を見て紀伊への道に立って、真土山 を越えてゆく。黄葉の散り飛ぶ光景を見ながら、すっかり慣れ親しんだ私のことは忘れ、旅はいいものだとあなたは 思っておいでだろうと、うすうす気づいています。けれども黙ってじっとしてられなくて、あなたの後を追っていこ うと、いくたび思ったことか。けれど、か弱い女の身である私、関所の番人に問いつめられたら何とこたえていいか 分からず、立ちすくんだまま途方に暮れるばかりでしょう。
反歌
4-544
・遺居<而> 戀管不有者 追及武 道之阿廻尓
標結吾勢
後れ居て恋ひつつあらずは追ひ及かむ道の隈廻に標結へ我が背
家にじっとしていて、恋い慕ってなどいないで追いかけていこうじゃありませんか、道の曲がり角毎に目印の標を結んでおいてね、私のあなた。
.jpg) 紀伊国分寺
紀伊国分寺
聖武天皇の勅願で、全国60カ所に建立された国分寺のひとつ。現在は史跡公園として、江戸時代に建てられ保存修理された本堂や当時の原型を残す七重塔跡の礎石が残ります。寺域や伽藍配置が明確で、南海道諸国との類似性がわかる貴重な遺跡。南側にある「紀の川市歴史民俗資料館」で出土遺跡を所蔵、国分寺の歴史を学べます。
4−1195
・麻衣 著者夏樫 木國之 妹背之山二 麻蒔吾妹
| 麻衣着ればなつかし紀の国の妹背の山に麻蒔く我妹 |
麻衣(あさごろも)を着ると、紀の国の妹背の山に麻の種を蒔く彼女がなつかしくなる。
| 藤原卿 |
この藤原卿とは誰のことか。神亀元年724年10月の聖武帝の紀伊半島のときに、藤原房前あるいは麿が作ったとされているが、この「卿」という尊称は三位以上の者につけられる
ものであるので、藤原房前であろう。彼は不比等が父とする藤家四兄弟の次男で藤原北家の祖である。思うに、これは奈良時代の歌であろうか。

藤原南家(ふじわら なんけ)とは、奈良時代の藤原不比等の長男である藤原武智麻呂に始まる藤原氏の一流。「南家」の称は、武智麻呂の邸宅 が弟房前の邸宅に対し南に位置したことに由来する。子孫は、朝廷内では房前を祖とする藤原北家に押されて振るわなかったが、為憲流 藤原南家の工藤氏・伊東氏・二階堂氏・泉田氏・相良氏など武家の名族を数多く輩出した。
藤原北家(ふじわらほっけ)とは、右大臣藤原不比等の次男藤原房前を祖とする家系。藤原四家の一つ。藤原房前の邸宅が、藤原南家の祖であ る兄の藤原武智麻呂の邸宅よりも北に位置したことがこの名の由来。
藤原式家(ふじわらしきけ)とは、右大臣藤原不比等の三男藤原宇合を祖とする家系。宇合が式部卿を兼ねたことから式家と称した。
藤原京家(ふじわらきょうけ)とは、右大臣藤原不比等の四男藤原麻呂を祖とする家系。藤原四家の一つ。藤原麻呂が左京大夫を兼ねたことがこの 家名の由来。
7-1098
|
「紀路」は紀州国または紀州国へ行く道。「妹山」は、古くは名のない山で、紀の川の南岸の「背の山」に向き合う山として名付けられたといいます。「玉櫛笥」は「二上山」の枕詞。「二上山」は大和国原の真西にあり、男嶽(おだけ・515m)と女嶽(めだけ・474m)と頂上が二つに分かれています。フタカミは二つの神の意で、「あめのふたかみ」と呼び、「天二上嶽」と書きます。古くから神の山としてあがめられていました。 非業の死を遂げた大津皇子の墓があるのは二上山の男嶽です。
7-1193
・勢能山尓 直向 妹之山 事聴屋毛 打橋渡
背の山に直に向へる妹の山事許せやも打橋渡す
背の山と妹の山ははまっすぐに向き合っている 背の山の口説きに妹の山は承諾したのだろうか。
川に打橋が架かっている。
7-1208
・妹尓戀 余越去者 勢能山之 妹尓不戀而 有之乏左
妹に恋ひ我が越え行けば背の山の妹に恋ひずてあるが羨しさ
彼女が恋しくて山越えに難渋しているが、すでに彼女(妹の山)を得ている背の山が羨ましい。
7-1209
・人在者 母之最愛子曽 麻毛吉 木川邊之
妹与<背>山
人ならば母が愛子ぞあさもよし紀の川の辺の妹と背の山
紀の川の両岸に仲良く並ぶ妹の山と背の山は、人間ならさしづめ母と最愛子(まなご)という風情である。
7-1210
・吾妹子尓 吾戀行者 乏雲 並居鴨 妹与勢能山
我妹子に我が恋ひ行けば羨しくも並び居るかも妹と背の山
彼女のことを恋しい思いで旅路を行くと妹の山と背の山が並び立っていて羨ましいかぎり。
7-1247
| 大穴道 少御神 作 妹勢能山 見吉 大汝少御神の作らしし妹背の山を見らくしよしも 大国主命(おおくにぬしのみこと)と少彦名命(すくなひこなのみこと)がお作りになっ た妹背の山は見るからに素晴らしい。 |
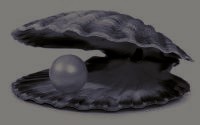
13-3319
・木國之|濱因云|<鰒>珠|将拾跡云而|妹乃山|勢能山越而|行之君|何時来座跡|玉桙之|道尓出立|夕卜乎|吾 問 之可婆|夕卜之|吾尓告良久|吾妹兒哉|汝待君者|奥浪|来因白珠|邊浪之|緑<流>白珠|求跡曽|君之不来益 |拾 登曽|公者不来益|久有|今七日許|早有者|今二日許|将有等曽|君<者>聞之二々|勿戀吾妹
紀の国の|浜に寄るといふ|鰒玉|拾はむと言ひて|妹の山|背の山越えて|行きし君|いつ来まさむと|玉桙の|道に出 で立ち|夕占を|我が問ひしかば|夕占の|我れに告らく|我妹子や|汝が待つ君は|沖つ波|来寄る白玉|辺つ波の| 寄する白玉|求むとぞ|君が来まさぬ|拾ふとぞ|君は来まさぬ|久ならば|いま七日ばかり|早くあらば|いま二日ばかり |あらむとぞ|君は聞こしし|な恋ひそ我妹
紀の国の浜に寄せられるという鰒玉(あはびたま)(真珠)を拾おうといおっしゃって、妹の山
背の山越えていかれたあの人。いつ帰って来るのだろうと、道に出て立って(道祖神に)夕占いをお願いしたら、夕占いが出て私におっしゃった。『愛しい人よ、そなたが待っている彼は、沖の方から波に寄せられてくる真珠、岸辺に寄せられてくる真珠を求めようとしているので来られない。あるいはその真珠を拾おうとしているので来られない。が、遅くなっても七日間、早ければあと二日間待ってほしいと言いなすった。なのでそんなに恋しがらないでくれ』と・・・。
妹山の出現について
妹背の山々が『万葉集』に初出するのは、4−544番歌であろう。合わせて妹山と背山の呼び名についての問答歌が、3-285と286に出ていますが、この背山の名称替えをめぐり 2人の問答の内容を考慮すると、妹山の出現過程は次のように推測できる。
すなわち、もともと存在したのは「セノヤマ」(『日本書記』大化2年〔646〕正月1日条に「兄山」と記されている)なのであった。その「セノヤマ」の「セ」に「背」の連想が及び、さらに
その「背」との連想で「妹」が浮上し、その先に「妹山」の出現をみたものと考えられる。
また、万葉集学者の俗説を否定した村瀬論を紹介する。。
、、、、、、村瀬博士の群述したように、万葉集に詠まれた紀伊の国の妹山が、紀ノ川をはさんで背山の対岸にあるいわゆる長者屋敷の岡がそれであると見られてきた(通説)のも、実は古今集当該歌の影響によるものであった。紀伊国の背山と妹山を割って流れることはなかった。それにもかかわらず、紀ノ川の対岸に妹山を求めたのは、古今集当該歌の構図(吉野川を中にして両山があるという構図)に縛られたためであった。
参考文献 (『万葉集の妹山・背山』 村瀬憲夫 )